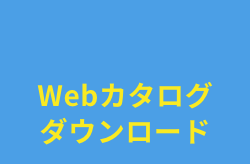BLOG
工務ブログ

2025.04.18
田島
「尺貫法」ってご存知ですか?
こんにちは!
いつもブログをご覧いただき
ありがとうございます。
シンプル工務店 現場監督の田島です!
今日はちょっとマニアックなお話しですが、
現場ではまだまだ活躍している
「尺貫法」についてご紹介します。
名前は聞いたことあるけれど、
実際どう使われてるの?って思う方、
多いのではないでしょうか?
でもこの尺貫法、住宅づくりには
今でも欠かせない存在なのです。
尺貫法とは、
昔の日本で使われていた長さや
重さの単位です。
今はメートルやキログラムが一般的ですが、
建築や伝統工芸の現場では、
今でも自然と使われています。
長さの基本は「尺」。
1尺はおよそ30センチ。
ちょうど大人の前腕くらいで、
感覚的にとても分かりやすいです。
さらにその10分の1が「寸」、6尺分が「間」
と呼ばれる単位です。
この「間」が住宅づくりの基本となっていて、
柱と柱の間や部屋のサイズの
基準にもなっています。

【不動産豆知識】体の大きさが元になった「尺貫法」(705) | その他に関するコラム | マンション・不動産情報なら大京穴吹不動産
参照
たとえば和室の畳。畳1枚は1間×半間。
つまり約180センチ×90センチくらい。
昔ながらの日本の家は、空間が無理なく
スッと収まっていると思いませんか?
それはこの単位が暮らしに
フィットしているからなのです!
実際に現場でよくあるのが、
「この壁を2寸前に出そう」や
「1間半で区切ろう」といった会話。
サッシや建具のサイズも
「3尺幅」や「6尺高」など、
尺貫法で設計されていることが多いです。
図面に「910」なんて書かれていたら、
それは3尺のこと。
職人さんたちの会話も、
自然とこの単位で進んでいきます。
重さの単位では「貫」という言い方も
まだ生きています。
昔ほどではございませんが、
金物や伝統工芸の現場では
今も見かけることがあります。
ちなみに1貫はお米の袋ひとつ分くらいの
イメージですね。
一見すると、
古くさい印象があるかもしれませんが、
尺貫法はとても理にかなった単位なのです!
人の身体を基準にしているので、
使っていて気持ちがいい。
そして木造住宅の寸法にもぴったり合う。
だからこそ、今でも日本の住宅現場では
大事に使われているんですね。
最近では図面やソフトが
メートル法に統一されつつありますが、
それでも現場で作業をする私たちには、
尺の感覚があるかどうかがとても大きいです。
図面と現場の「間」を埋めてくれる、
そんな役割も担ってくれている気がします。
というわけで、ちょっと懐かしくて、
でも今もリアルに使われている尺貫法。
家づくりに興味がある方は、
ぜひこの日本ならではの単位の世界も、
ちょっと覗いてみてくださいね!


それでは、また!
田島